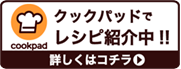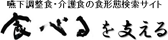導入事例

長崎リハビリテーション病院
「嚥下機能向上に寄与する食事」を目指して
効率的で質の高い嚥下調整食の提供を可能とするために既製品介護食を活用
施設分類:回復期リハビリテーション病院
ベット数:143床
西岡心大さん(上段右)および栄養管理室、㈱LEOCの皆様
-
食形態ごとの内訳
コード コード0j コード1j コード3 コード4 名称 嚥下食レベル1 嚥下食レベル2 嚥下食レベル3 嚥下食レベル4 対象人数 0 ※訓練用のゼリーとしては随時提供 0 5 9 -
嚥下調整食を導入する際のポイントや流れ
1.理由
2008年開院時より導入していました。嚥下障害を抱える方が多いため、嚥下調整食を導入しないという発想がありませんでした。
2.流れ
前職で提供していた段階、ノウハウをアレンジして使用
医師、言語聴覚士とともに食形態や物性の安全性を検討しました。
3.ポイント
当院理事長のポリシーで見た目・味・匂いなどにこだわり美味しい嚥下食を提供することにこだわっています。
4.工夫点
開院直後に多職種(医師・看護師・管理栄養士・言語聴覚士・歯科衛生士・給食委託業者等)による嚥下食ワーキンググループを発足させ、新メニューの開発や真空調理など新調理法の採用などを行いました。
5.役割
回復期リハビリテーション病棟では、経管栄養から経口摂取に移行する方が多く、嚥下調整食の意義は非常に大きいと思います。イメージは「現在の嚥下機能に合わせた形態の食事」というより、「嚥下機能向上に寄与する食事」です。つまり安全な物性というだけでは不十分で、見た目・味・匂いなどを兼ね備え、食べる意欲がわくような嚥下食が回復期では望ましいと考えています。
-
どんな風に活用しているか
主に嚥下食レベル3(コード3相当)の主菜・副菜として使用しています。
-
既製品を使うことのメリット
作業負担の軽減、味・物性の均質化が大きいと思います。これにより生じた空き時間を他の手のかかる工程(盛り付けなど)に充てられるため、効率的で質の高い嚥下調整食の提供が可能となっています。
-
費用について
手作りにした場合の手間・人件費を考慮すれば、既製品の費用はそれほど割高ではないと感じます。
-
献立例
-
関連商品