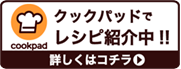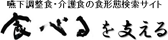導入事例

武蔵野赤十字病院
地域連携としての役割
統一した形態・物性のものを提供するため既製品介護食を活用
施設分類:急性期病院
ベット数:611床
松野さおりさん(下段左)および栄養課の皆様
-
食形態ごとの内訳
コード コード0j コード1j コード2 コード3 コード4 名称 嚥下開始食 嚥下半固形食 嚥下ペースト食 嚥下ソフト食 嚥下きざみとろみ食 対象人数 2 3 5 6 11 -
嚥下調整食を導入する際のポイントや流れ
1.理由
地域で嚥下食が統一されていないこと等が問題としてあげられ、地域連携を進めるために導入しました。
2.流れ
メーカーへ商品の案内・調理実習を依頼⇒栄養課内、摂食嚥下認定看護師との試食会を実施。
3.ポイント
厨房担当者と、限られた調理時間の中でコード分類の展開方法を相談しました。
4.工夫点
嚥下調整食を召し上がる方は耐久性の低い方も多いため、少量で高エネルギーになるようMCTオイル添加の主食に変更しました。
5.メリット
転院や退院の際に学会分類を表記しての情報提供が行えるようになりました。
6.急性期病院としての役割
嚥下機能に見合った食事の提供、食形態を含む食事の情報を在宅や慢性期病院に正確に伝え、途切れさせないことが重要だと思います。
-
どんな風に活用しているか
当院では、主菜はマルハニチロさんのNew素材deソフトをコード4として使用し、コード3・2はそれをミキサーにかけてゲル化剤を使用し展開しています。
-
既製品を使うことのメリット
調理担当者が変わっても、統一した形態・物性のものを提供できることが一番のメリットだと思います。
また、既製品を使うことで調理に関わる人件費を抑えられることも一つのメリットだと思います。
-
費用について
入院患者さんは高齢化に伴い、複雑な疾患(多数の疾患)をもって入院することから、個別対応の患者数が非常に増えております。そのため、厨房での調理作業や盛り付け作業、それ関わる個別対応の献立作成・発注なども非常に複雑化し、その作業に人員が取られてしまうため、作業の効率化・合理化を図る必要性がありました。
嚥下調整食の既製品は高額の印象はありますが、人件費や食材ロス、光熱費を総合的に考えると費用対効果は十分にありますので、委託会社に相談して、導入することにしました。食材費だけにとらわれず、給食管理全体の視点で考えることが重要だと感じています。
また、現在の診療報酬では嚥下機能低下の患者さんは栄養食事指導料の算定対象であり、栄養管理計画書やNSTの治療計画書にも嚥下調整食の記載は学会分類で書くことが求められているため、基準に合わない食事提供をすることは問題になると考えています。
-
献立例
-
関連商品